Non- Diatonic Chordsの機能
目次
代理和音として使用する事のできるnon-diatonic chord は次の様に分類されますが、それらは基本的に調性の枠にとらわれる事はありません。
A) Tonic chord の代理和音
●Major keyのTonic chord は I △7(6)ですが、「Blues」においてTonic chord はBlue note scaleの使用によりI 7 として現われます。
この和音はBluesy 7th chord として分類され、今ここで取扱われているMajor key に於けるTonic chordの代理和音、IIIm7、VIm7等とは、そのchordの機能が根本的に異質のものです。 したがって I 7 chord はここではMajor key のTonic chord の代理和音としては分類していません。
B) Dominant chord の代理和音
⚫︎bII7、V7 chordと共通のTritoneを内含するchord
(Key- C or Cm)

C) Sub- Dominant Chord の代理和音
IV7
Major keyにおいて、本来 IV△7 chord であるはずの和音の M.7th 音が m.7th 音に 変化した時、IV7 chordとして現われる。この和音は Blues Feeling を加味する目 的で使用されると解釈出来ます。
(Key- C )
また「Blues」における Sub-dominant chordは Blue note scaleの使用により IV7 として現れます。この和音もまたBluesy 7th chord として分類されます。
minor key においてIV7 はmelodic minor scale chordsの sub- dominantの和音であり、Diatonic chordとしてすでに分類されています。
VII7
IV7 chord と共通のTritone を内包する chord.
(Key- C)
#IVm7(b5)
本来 VII7 chord のTwo-Fiveとして現れますが、そのまま独立して使用されたものと考えられます。
(Key- C)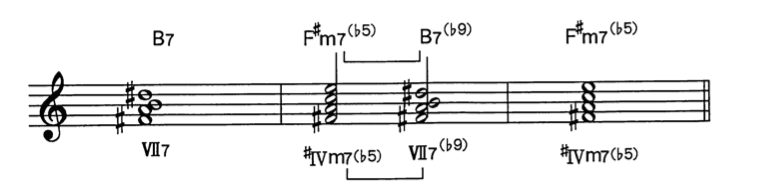
minor keyにおいて #IVm7(b5) chord はSub-dominant chord の代理和音とは分類し難いです。
D) Sub- dominant minor chord の代理和音
bII△7
IVm7 chordの変化和音として分類されます。
(Key- Cm)

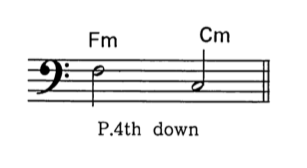
またrootが半音進行する事によりsub -dominant Cadence を形成します。
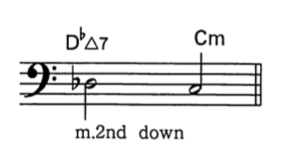
bVI7
bVI△7 chord の M.7th 音が m.7th 音に変化した時 bVI7 chord として現れます。 この和音もまたBlues Feeling を加味する目的で使用されると解釈出来ます。
(Key- Cm)
「Blues」においてこの和音もBluesy 7th chord として分類されます。
これらの和音もDiatonicの時と同様、借用和音として同主長調において多く使用されます。
Non-Diatonicchordの機能表
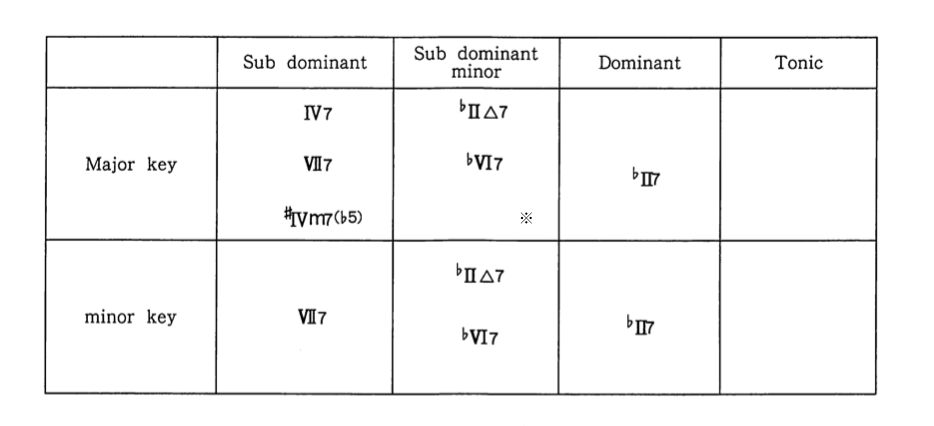
※ Major KeyのSub- dominant minor の借用和音としてしばし使われる場合があります。
→ Passing Diminished へすすむ

